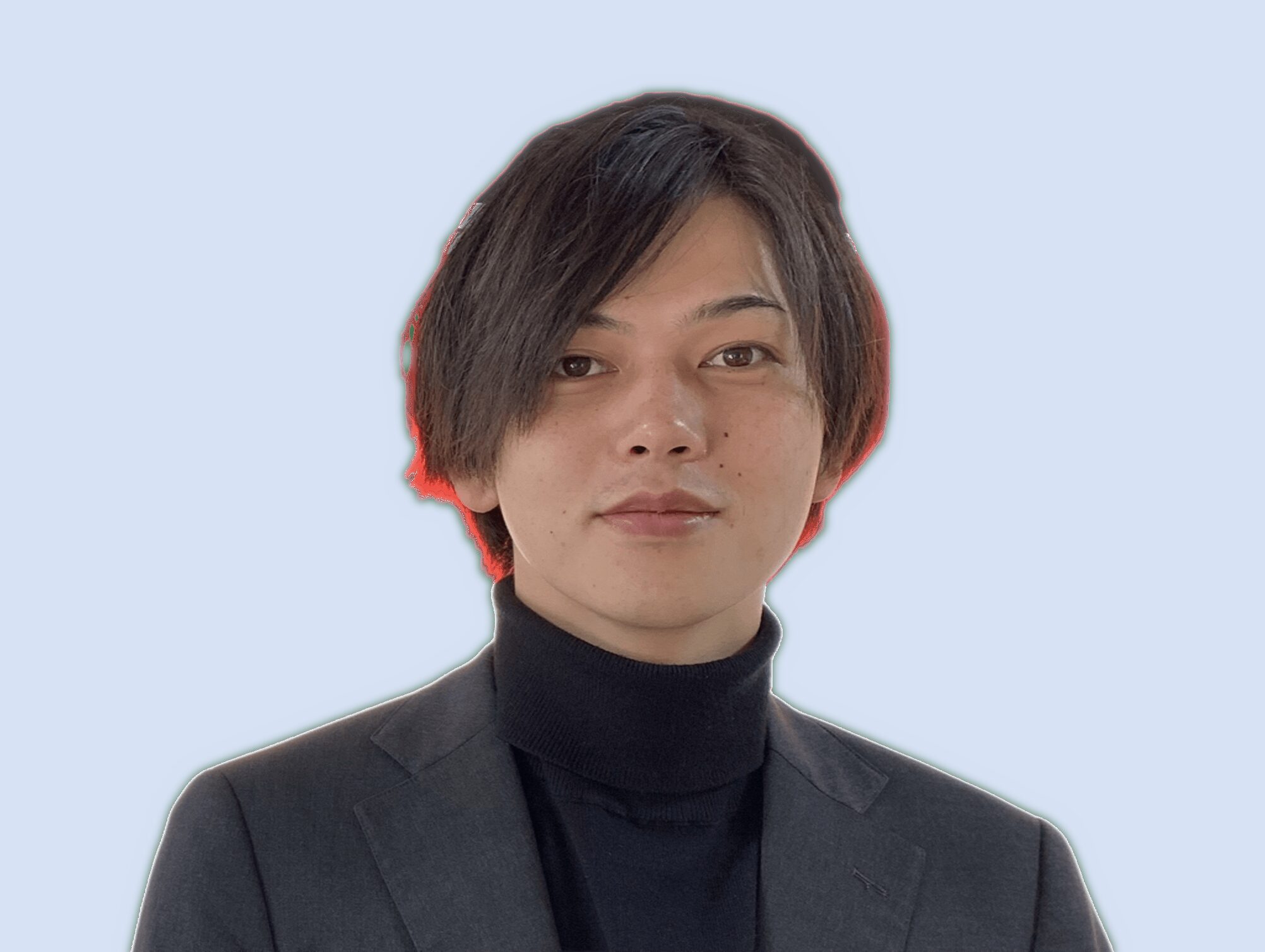賃貸のエアコンが故障!修理費用は誰が負担?そんなトラブルを未然に防ぐため、この記事では「残置物」「サービス品」「設備」の明確な違いを徹底解説します。所有権は誰にあり、修理や撤去の責任はどこにあるのか、借主・貸主双方のメリット・デメリットまで、図解を交えて分かりやすく説明。後悔しない物件選びの結論は、契約前に賃貸借契約書や重要事項説明書で、その備品の所有者と修繕義務の所在を必ず書面で確認することです。
1. 賃貸物件の残置物・サービス品・設備とは 3つの基本を解説
賃貸物件を探していると、エアコンや照明器具、ガスコンロなどが付いていることがあります。しかし、それらが「残置物」「サービス品」「設備」のどれにあたるかによって、故障したときの対応や退去時の扱いが大きく変わってきます。これらの違いを正しく理解していないと、「突然の故障で修理費を自己負担することになった」「退去時に撤去費用を請求された」といった予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
まずは、賃貸契約における基本となる「残置物」「サービス品」「設備」それぞれの定義を、具体例を交えながら詳しく見ていきましょう。
1.1 前の入居者の忘れ物?「残置物」の定義
「残置物(ざんちぶつ)」とは、前の入居者が退去する際に、所有権を放棄して物件に残していった私物のことを指します。本来であれば、退去時にすべて撤去されるべきものですが、大家さん(貸主)の許可のもと、次の入居者が利用できるようにそのまま置かれているケースがあります。
例えば、以下のようなものが残置物として扱われることがあります。
- エアコン
- 照明器具
- ガスコンロ
- 冷蔵庫・洗濯機
- カーテンレール・カーテン
- ウォシュレット(温水洗浄便座)
- 食器棚や収納棚
残置物における最も重要なポイントは、物件の「設備」ではないため、大家さんに修理義務がないという点です。あくまで「おまけ」のような存在であり、性能や動作の保証はありません。もし故障してしまっても、大家さんは修理や交換をしてくれないのが原則です。修理して使い続けるか、大家さんの許可を得て自費で撤去・処分するかは、入居者(借主)の判断と負担に委ねられます。
1.2 大家さんのご厚意?「サービス品」の定義
「サービス品」とは、大家さん(貸主)が自身の所有物の中から、入居者の利便性のために善意で設置した物品のことです。残置物と混同されがちですが、前の入居者の私物ではなく、大家さん自身の所有物であるという点で異なります。入居者を早く決めるための付加価値として設置されることが多く、「設備」とは明確に区別されます。
サービス品としてよく見られるのは、以下のようなものです。
- インターネット用のWi-Fiルーター
- 電子レンジ
- テレビ
- 小規模な家具(ベッド、テーブルなど)
サービス品も残置物と同様に、賃貸借契約における「設備」には含まれません。そのため、契約書に「サービス品の故障については貸主は修繕義務を負わない」といった特約が記載されているのが一般的です。つまり、故障した場合は入居者が自費で修理するか、使用を諦めるかを選択することになります。所有権は大家さんにあるため、勝手に処分することはできません。退去時には、原則として元の状態に戻して置いていく必要があります。
1.3 物件にもともと付いている「設備」の定義
「設備」とは、その賃貸物件の一部として、もともと備え付けられている機能や機器を指します。これらは賃料に含まれる要素であり、入居者が安全で快適な生活を送るために、大家さんが提供する義務を負うものです。
物件の設備にあたるものの代表例は以下の通りです。
- キッチン(シンク、コンロ台)
- 浴室・トイレ
- 給湯器
- 備え付けのエアコン
- インターホン
- クローゼットや押入れなどの収納
- 建付けの建具(ドア、窓)
設備が最も重要な点は、経年劣化や通常の使用による故障が発生した場合、その修理・交換の義務と費用負担は原則として大家さん(貸主)にあることです(民法第606条第1項)。もし給湯器や備え付けエアコンが壊れた場合、入居者は速やかに大家さんや管理会社に連絡すれば、修理の手配をしてもらえます。ただし、入居者の不注意や故意による故障(善管注意義務違反)の場合は、入居者が修理費用を負担しなければならないため注意が必要です。
2. 一目でわかる 残置物・サービス品・設備の明確な違いを徹底比較
賃貸物件を探していると、「エアコン付き」と書かれていても、そのエアコンが「設備」なのか「残置物」なのかで、あなたの責任範囲は大きく変わります。これら「残置物」「サービス品」「設備」は、見た目は同じでも法律上の扱いやトラブル時の対応が全く異なります。まずは、それぞれの違いを一覧表で確認し、全体像を把握しましょう。
| 項目 | 残置物 | サービス品 | 設備 |
|---|---|---|---|
| 所有権 | 前の入居者 or 大家さん(貸主) | 大家さん(貸主) | 大家さん(貸主) |
| 故障時の修理費用負担 | 原則、入居者(借主) | 契約による(多くは借主負担) | 原則、大家さん(貸主) |
| 退去時の扱い | 契約による(撤去 or そのまま) | そのまま残す | そのまま残す |
| 契約書上の記載 | 「残置物」「性能保証なし」などと明記 | 「サービス品」「無償貸与」などと明記 | 「設備」として記載 |
この表からもわかるように、特に注意すべきは「残置物」です。故障した際の修理費用や、退去時の扱いについて、契約前にしっかりと確認しなければ、予期せぬ出費やトラブルに見舞われる可能性があります。ここからは、それぞれの項目について、さらに詳しく掘り下げて解説していきます。
2.1 所有権は誰にあるのか
物件にあるものが誰の持ち物なのかは、トラブルを防ぐ上で最も基本的なポイントです。所有権の所在によって、修理や撤去の責任者が変わってきます。
2.1.1 残置物の所有権
残置物の所有権は、非常に曖昧で注意が必要です。基本的には、前の入居者に所有権があります。しかし、前の入居者が所有権を放棄し、それを大家さん(貸主)が引き取った場合は、大家さんの所有物となります。いずれにせよ、あなた(借主)の所有物ではないため、勝手に処分することはできません。
2.1.2 サービス品の所有権
サービス品の所有権は、明確に大家さん(貸主)にあります。大家さんが「ご厚意で自由に使ってください」と提供しているもので、あくまで物件の付加価値を高めるためのものです。そのため、借主が勝手に交換したり、処分したりすることは認められません。
2.1.3 設備の所有権
設備は、物件の一部として扱われるため、所有権は大家さん(貸主)にあります。エアコン、給湯器、コンロ、備え付けの照明器具などがこれにあたります。これらは家賃に含まれる物件の構成要素であり、借主が所有権を主張することはできません。
2.2 故障した場合の修理費用は誰が負担するのか
入居後にエアコンや給湯器が故障した場合、その修理費用を誰が負担するのかは、生活に直結する重大な問題です。この責任の所在が、残置物・サービス品・設備で大きく異なります。
2.2.1 残置物が故障した場合
残置物が故障した場合、修理費用は原則として入居者(借主)の自己負担となります。大家さんには、残置物に対する修繕義務がありません。「前の入居者が置いていったものを、そのまま使わせてもらっているだけ」という位置づけだからです。たとえ真夏にエアコンが壊れても、大家さんに修理を要求することはできず、自分で修理するか、買い替えるか、我慢するかの選択を迫られます。
2.2.2 サービス品が故障した場合
サービス品の場合、修理費用の負担者は賃貸借契約書の内容によって決まります。契約書に「サービス品の修繕は借主の負担とする」といった特約が記載されているケースが多く、その場合は借主が費用を負担します。大家さんに修繕義務はないのが一般的ですが、契約内容を必ず確認しましょう。
2.2.3 設備が故障した場合
設備が故障した場合、原則として大家さん(貸主)が修理費用を負担します。これは、民法において、貸主は賃借人が問題なく使用できるように物件を維持する義務(修繕義務)を負っているためです。ただし、借主の不注意や故意による故障(例:掃除中に物をぶつけて壊した、子どもがいたずらで破損させた等)の場合は、借主の負担となるため注意が必要です。
2.3 退去する時の扱いはどうなるのか
賃貸物件から退去する際には、入居時の状態に戻す「原状回復義務」がありますが、残置物・サービス品・設備の扱いはそれぞれ異なります。勝手な判断で処分したり持ち出したりすると、後で費用を請求される可能性があります。
2.3.1 残置物の退去時の扱い
残置物の退去時の扱いは、入居時の契約内容によって大きく異なります。契約書や「残置物確認書」に「退去時に借主の責任で撤去すること」と記載されていれば、その指示に従わなければなりません。もし、自分で新しいものに買い替えた場合、もともとあった残置物と新しいものの両方を処分する必要が出てくる可能性もあります。逆に「そのまま置いていって良い」とされている場合もありますので、必ず契約内容を確認しましょう。
2.3.2 サービス品の退去時の扱い
サービス品は大家さんの所有物ですので、退去時にはそのままの状態で残しておく必要があります。勝手に処分したり、次の引越し先に持っていくことは絶対にできません。もし故障していても、大家さんの許可なく処分してはいけません。
2.3.3 設備の退去時の扱い
設備もサービス品と同様に、物件の一部であり大家さんの所有物です。したがって、退去時には入居した時の状態のまま残しておかなければなりません。設備のグレードアップなどを理由に、無断で交換・撤去することは契約違反となり、原状回復費用を請求される原因となります。
3. 【借主向け】残置物・サービス品がある賃貸物件のメリット・デメリット
「家具・家電付き」と聞くと、とてもお得に感じる残置物やサービス品がある物件。実際に大きなメリットがある一方で、知らずに契約すると後悔につながる可能性も秘めています。ここでは、借主(入居者)の視点から、メリットとデメリットを具体的に掘り下げていきましょう。
まずは、メリットとデメリットのポイントを一覧で確認してみましょう。
| 比較項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 費用面 | 家具・家電の購入費用や設置費用が不要で、初期費用を大幅に削減できる。 | 故障時の修理・交換費用や、不要な場合の撤去・処分費用が自己負担になる可能性がある。 |
| 利便性 | 入居後すぐに生活を始められる。引っ越しの荷物が減り、手間と費用が省ける。 | 自分の好きなデザインや性能の製品を選べない。型が古く電気代がかさんだり、性能が低い場合がある。 |
| リスク | 短期契約の場合、家具・家電を揃える無駄を省ける。 | いつ故障するかわからない不安がある。衛生状態が不明な場合もある。 |
3.1 初期費用が抑えられるメリット
残置物やサービス品がある物件の最大の魅力は、なんといっても新生活にかかる初期費用を劇的に抑えられる点です。通常、引っ越しには敷金・礼金だけでなく、生活に必要な家具や家電を揃えるためのまとまった費用が必要になります。
例えば、以下のような家具・家電が最初から室内にあれば、どれくらいの費用が節約できるでしょうか。
- エアコン:本体価格と設置工事費で10万円以上かかることも珍しくありません。特に複数の部屋に設置する場合、大きな負担となります。
- 照明器具:各部屋に必要で、合計すると数万円になることがあります。
- ガスコンロ:都市ガス用・プロパンガス用など種類があり、物件に合わせて購入する必要がありますが、備え付けならその手間と費用がかかりません。
- 冷蔵庫・洗濯機:大型家電は高額な上、搬入の手間や費用もかかります。これらが揃っていれば、引っ越し業者の料金プランも安くなる可能性があります。
これらの購入費用が浮くだけでなく、引っ越しの荷物そのものが減るため、引っ越し作業の手間や業者に支払う費用も削減できます。特に、初めての一人暮らしや、転勤などで一時的に住む場合など、家具・家電をすべて揃える必要がない方にとっては非常に大きなメリットと言えるでしょう。
3.2 修理や撤去費用が発生するデメリット
メリットが大きい一方で、残置物・サービス品には「タダほど高いものはない」ということわざが当てはまるような、思わぬ落とし穴も存在します。契約前に必ず理解しておくべきデメリットを3つの観点から解説します。
3.2.1 故障時の修理・交換は自己負担が原則
最も注意すべき点は、残置物やサービス品が故障した場合、その修理費用は原則として入居者の自己負担になることです。これらは物件の「設備」ではないため、大家さん(貸主)には民法上の修繕義務がありません。
例えば、真夏にエアコンが突然動かなくなっても、大家さんに修理を依頼することはできません。自分で修理業者を手配するか、新品を購入して設置する必要があり、高額な出費が発生してしまいます。「無料で使えてラッキー」と思っていたものが、結果的に大きな負担に変わるリスクがあるのです。
また、前の入居者が置いていったものであるため、製品が古く、いつ寿命がきてもおかしくない状態かもしれません。性能保証がない、いわば「現状渡し」であることを十分に認識しておく必要があります。
3.2.2 不要な場合の撤去費用も自己負担
「備え付けの冷蔵庫は容量が小さいから、自分で買ったものを使いたい」「部屋の雰囲気に合わないから、照明器具を交換したい」といったケースも考えられます。
しかし、残置物やサービス品はもともとそこにあった物なので、不要だからといって勝手に処分することはできません。もし処分したい場合は、まず大家さんや管理会社に許可を得る必要があります。許可が得られたとしても、粗大ごみの処分費用や家電リサイクル料金などは、自己負担となるのが一般的です。勝手に処分してしまうと、退去時に原状回復義務違反として、同等品の購入費用を請求されるなど、深刻なトラブルに発展する可能性があります。
3.2.3 衛生面や性能面での不安
前の入居者がどのように使用していたかわからないため、衛生面が気になる方もいるでしょう。特にエアコン内部のカビや、洗濯槽の汚れなどは、見ただけではわかりません。専門業者によるクリーニングがされておらず、自分で清掃費用を負担しなければならないケースもあります。
さらに、製品の型が古い場合、最新のモデルに比べて性能が劣ることも少なくありません。例えば、古いエアコンは省エネ性能が低く、毎月の電気代が想定より高くなってしまうことも考えられます。初期費用は抑えられても、ランニングコストがかさんでしまい、結果的に損をしてしまう可能性も視野に入れておきましょう。
4. 賃貸契約で後悔しないための重要チェックポイント
「残置物だとは知らなかった…」「故障したのに修理してもらえない…」そんな賃貸トラブルは、契約前のほんの少しの注意で防ぐことができます。口頭での説明だけでなく、必ず書面で内容を確認し、納得した上で契約に進むことが何よりも重要です。ここでは、後悔しないために絶対に押さえておくべき3つの重要チェックポイントを具体的に解説します。
4.1 重要事項説明書と賃貸借契約書の確認箇所
宅地建物取引士から説明を受ける「重要事項説明書」と、貸主と交わす「賃貸借契約書」は、トラブルが起きた際の最も強力な根拠となる書類です。特に以下の項目は、残置物・サービス品・設備に関する取り決めが記載されている可能性が高いため、一言一句見逃さずに確認しましょう。
| 確認すべき項目 | チェックポイントと具体的な記載例 |
|---|---|
| 設備一覧 / 付帯設備表 | 物件に「設備」として何が含まれているかがリストアップされています。ここに記載されているものは、基本的に貸主の所有物であり、故障時の修理義務も貸主にあります。
エアコン、給湯器、ガスコンロ、照明器具などの記載があるか、現物と相違ないかを確認しましょう。 |
| 特約事項 | 契約における特別なルールが記載される項目です。残置物やサービス品に関する取り決めは、この特約事項に書かれているケースが非常に多いです。曖昧な表現がないか、不利な内容になっていないかを精査する必要があります。
【記載例】
|
| 修繕義務の範囲 | 誰がどの部分の修理費用を負担するのかを定めた項目です。「設備の修繕は貸主の負担」「借主の故意・過失による故障は借主の負担」といった一般的な記載に加え、残置物やサービス品の修繕義務が明確に「借主負担」とされているかを確認します。 |
| 原状回復義務 | 退去時に部屋を入居時の状態に戻す義務について定めています。残置物がある場合、退去時にその残置物をどう扱うべきか(撤去が必要か、そのまま残してよいか)が特約事項などに記載されていることがあります。「残置物の撤去費用は借主負担」といった一文がないか必ず確認してください。 |
4.2 内見時に設備の動作確認と写真撮影を
書類の確認と並行して、内見時の現物確認は絶対に行うべき重要なステップです。図面や書類だけではわからない実際の状態を自分の目で確かめ、トラブルの芽を未然に摘み取りましょう。
4.2.1 動作確認のチェックリスト
内見時には不動産会社の担当者に許可を得て、以下の項目を一つずつ動かしてみることを強くお勧めします。
- エアコン:冷房・暖房・除湿などの各モードで正常に作動するか。異音やカビ臭いような異臭はしないか。リモコンの電池は切れていないか、ボタンは反応するか。製造年式も確認しておくと、電気代や故障リスクの目安になります。
- 給湯器:キッチン、洗面台、浴室でお湯がきちんと出るか。温度設定は正常に機能するか。
- ガスコンロ・IHヒーター:全てのコンロが問題なく点火・通電するか。火力の調整はスムーズか。魚焼きグリルも忘れずにチェックしましょう。
- 照明器具:全ての部屋の照明が点灯するか。リモコンがある場合は動作を確認します。
- 換気扇(キッチン・浴室・トイレ):スイッチを入れて正常に作動するか。異音はしないか。
- 温水洗浄便座:洗浄や暖房便座、乾燥などの各機能が使えるか。水漏れはないか。
4.2.2 証拠としての写真・動画撮影
動作確認と同時に、スマートフォンなどで写真や動画を撮影しておくことが、将来の自分を守るための保険になります。
特に、エアコンや給湯器の型番・製造年がわかるシール部分、入居時点であった壁や床の傷、設備の汚れなどを日付がわかるように撮影しておきましょう。これらの記録は、万が一故障した際の交渉材料になったり、退去時の原状回復費用を請求された際に「入居前からあったものだ」と証明する客観的な証拠として極めて有効です。撮影したデータは、退去時まで大切に保管しておきましょう。
5. まとめ
賃貸物件のエアコン等が「残置物」「サービス品」「設備」のどれにあたるかで、所有権や故障時の修理義務は大きく異なります。この違いを理解しないと、予期せぬ修理費用の負担など、思わぬトラブルに繋がる可能性があります。快適な新生活を始めるためにも、契約前に重要事項説明書や契約書を細部まで確認し、不明な点は不動産会社に必ず質問しましょう。事前の確認こそが、入居後の後悔を避ける最も確実な方法です。